 |
 |
 |
CSTB(建築研究所)でのHA研究
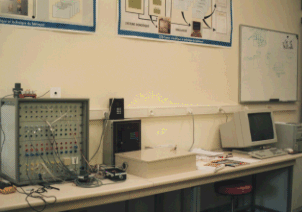 |
ニース郊外のソフィア・アンティポリスのリサーチ・パークにあるCSTB(Centre Scientifique et Technique du Batiment=建築研究所)を訪問。ここでは現在6人がホームオートメーションに関しての研究を行っている。
ここではPHI計画がらみでのHAシステムの評価を行っている。1987年からフランスの公共団体は、ホームオートメーション実験のナショナル・プロジェクトを開始している。
その主要なものが、1990年から始まったPHI(Interactive Dwelling)計画で、フランスの17カ所に様々な試行的な住宅を建設している。
フランスの場合、これまで公営住宅(HLM)がプレハブをはじめとする様々な先進的技術の試行の場として使われてきた。PHI計画に関しても、特別な支出枠が組まれ実験的な住宅が建設された。
PHI計画は住宅設備機器の自動化のためのマイクロプロセサーの利用、エネルギー管理のための「ドーモティック・コントロール・パネル」、ミニテルとその新たなサービスの開発、CATV、先進的なコンピュータ・マネジメント、テレビによるコミュニケーション、在宅学習・在宅ビジネス、電話を介したコントロールなどが含まれている。
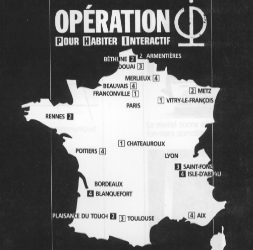 |
| (1) 住宅建設とHA技術 |
HA機器、システムの開発と、住宅設計手法、取り付け、施工方法の開発。
| (2) 規模とサービス |
住戸数によって可能なサービスの内容が異なってくる。個々のサービスごとの最適規模の把握。
| オートメーション |
| ホームマネジメント | コミュニケーション |
| オートメーション |
オートメーションそのものは人類がこれまで作ってきた機械の歴史に見いだすことができ、エレクトロニクス化によってそのメカニズムがやや洗練されたに過ぎない。
ホームオートメーションも結局のところ自動的に動くようにすることと自動的な制御であり、それが生活行動の中で"Here & Now=ここでいま"といった要求にいかに応えるかである。
| ホームマネジメント・ツール |
ガス、水、電気、暖房などの供給、保守や修理をコンピュータによっていかに管理するかもドーモティックの大きな技術的テーマになっている。
そしていかに効率的にするかであり、ネットワークを通して消費量を監視し、また機器の作動状況を遠隔監視し、保守修理をネットワークを通して行うのがホームマネジメント・ツールである。
しかしPHI計画ではこうしたサービスは、今のところ成功していない。監視センター側のソフトウエアが全く未整備の状況にある。
| コミュニケーション・ツール |
火災警報や進入警報など遠隔セキュリティーサービスだけでなく、PHI計画では、在宅支援(アシスタンス)サービス、在宅活動(ホームワーク)サービスの二つも含まれている。
在宅支援サービスは老人や身障者を対象としたもので、外部の支援サービスとリンクするためのハンズフリーのコミュニケーション・ツールが用意されている。
いっぽう在宅活動サービスは、学習、トレーニング、仕事などであるが、一緒に仕事をしたいとか、通勤による変化を求めたりすることが多いので、それほど現実的であるとは考えられていない。
またコミュニケーション・ツールに関しては、どんなサービスが可能か、どんなサービスが求められているか、さらにそれらに対応したツールの開発が必要であるが、開発担当者は汎用ツールや多目的サービスは主流にはならないだろうと考えている。
ミニテルはビデオテックスとして商業的に成功した唯一のものである。1970年代後半からイギリスではプレステル、日本ではキャプテン、アメリカではテリドンなどとして開発され、商用化された電話回線を通した文字画像情報システムであるが、フランスのミニテルを除いて、商業的には成功していない。
電話帳を廃止する代わりに、ミニテル端末の無料貸出を全国的に行ったのが普及のきっかけになっており、このようにフランスでは国家主導の情報化の推進が行われている。
ホームオートメーションおよび住宅の情報化についてもミニテル同様、あるいはミニテルとともに行政的支援策によって、フランスが他の国に先駆けて最も早く普及する可能性を持っている。
フランス・テレコムによると1987年に330万台、88年には440万台、89年には510万台、1990年には560万台のミニテルの端末が設置されている。全国民の29%が、またビジネスの分野では41%の人がミニテルとアクセスしている。
こうしたことからもミニテルをユーザーインターフェースとしたインテリジェント・ホームサービスの実用化の可能性は極めて高いと言える。
PHI計画の中で最大規模のものはMetzに建設された1415戸の集合住宅である。ここでは住戸内のターミナルとしてドーモボックスが開発され組み込まれている。
モデムを持ち外部ネットワークに接続されたドーモボックスの機能は、エネルギー管理、セキュリティーと通信機能で住設機器のコントロールは行わない。
ドーモボックスの本体に侵入者を感知する赤外線のディテクターが備えられている。放熱器のセンサーなどが接続され、将来はさらに集合玄関のビデオモニターと解錠機能が付けられる予定であるが、どう見てもこのターミナルはそれほどインテリジェントでなくスマートでない。
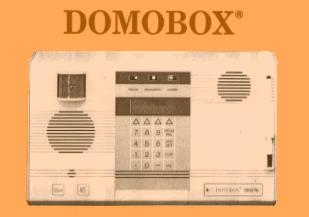 |
LEGRAND社のHA実験住宅
ルグラン社は配線機器、スイッチなどではフランス最大のメーカーで、7年前からHA関連機器の商品化を行っている。ルグラン社のHAシステムの特徴は現実的なことである。
シンプルなものから徐々にマーケットの動向を見ながら進めている。というのもフランスでは政府が積極的にHAの推進を行っているので、とかく実際のマーケットニーズとは掛けはなれることが多いという。照明のディマーでさえフランスではまだまだ売上が少ない。
本社の構内にHAの実験住宅を建設しているが、非公開の施設で一般には見学することができない。多くの開発中の製品が組み込まれ実験中で、しかも大きな夢を追い続けるのではなく、現実的なアプローチでHAシステムの商品化を行おうとしている。
 |
 |
 |
ベランダに出る引き違いサッシも電動で、リモコンにより開閉が可能である。この電動機構部分は後付け部品としても商品化できそうである。
 |
犯罪の少ない日本では需要が少ないが、フランスなどでは電動ブラインドや電動カーテン、照明を電話回線を通してリモートコントロールして、会社から帰りが遅くなるときに、いかにも帰っているように演出するといった装置も結構需要があるようである。
 |
 |
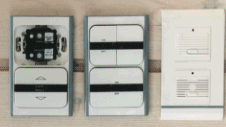 |
この右端のスイッチは、スピーカーとマイクロホンも兼ねていそうである。音声認識や音声合成技術はかなりのところまできている。さらに電灯線搬送を使えば、音声をパワーラインに載せることも可能である。
家の中の一箇所に音声サーバーを兼ねたパソコンを置いておくと、「開け胡麻」というような音声による制御、アシスタンス、警報も可能である。
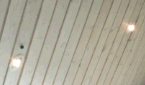 |
Windoiws95でも赤外線通信が組み込まれており、フレキシビリティーを追求すると音声によるコミュニケーションか赤外線によるコミュニケーションにならざるを得ない。
天井はどちらのコミュニケーションにとっても都合の良い端末設置場所となるに違いない。