 |
 |
 |
SED
常勤の職員もそれほど多くないが、単なる団体の事務局ではなく、ホームオートメーションに関しての具体的な実験研究を行っている。
ここでは主としてエルゴノミックス的側面からの機器のユーザーインターフェースの試験、HA機器の通信互換性の試験、HAシステムに関してのCAIシステムの開発を行っている。
たとえば多くのモニターが電源スイッチを探す様では、その位置が悪いということになる。モニターの操作の様子はマジックミラーでの観察の他、モニターカメラを通してビデオに録画される。もちろんジョイスティックで方向やズームなどは自在である。
モニター一人当りほぼ1時間のテストを行う。終了後アンケートも行われる。その後でビデオを見ながらベストな使い方との比較といった方法で細かな解析が行われ、テスト結果がメーカーにレポートされる。
 |
天井に取り付けられたビデオカメラ
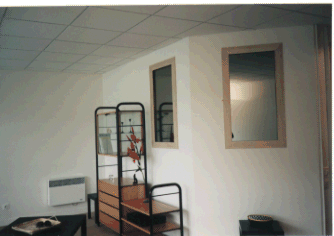 |
マジックミラーからの観察
 |
ジョイスティックでカメラを動かしながら録画
SED内部には各種のケーブル、バスラインが敷設されている。パーソナルコンピュータにエミュレーションボードが搭載し、さまざまなバスによるHA関連機器の通信互換性の試験が可能である。おおよそ2日程かけて互換性の試験が行われる。
4枚のビデオディスクを使ったインタラクティブな教育システムでを開発し、今年から具体的に活用を始める予定である。このうち3枚がドモティックの技術的解説で他の1枚がコンサルティング・セールスに関してのものである。
システムはパソコンとレーザーディスク・プレイヤーから構成され、マルティメディアのオーサリングシステムを使って開発された。テキスト、画像、音声、動画を駆使したものになっている。
このソフトの開発に3〜400万フラン(約6〜8000万円)かけており、今年から2万フラン(約40万円)で販売する予定である。これは近い将来わが国でも登場するであろう、HAコーディネータのための教育ソフトであるが、残念ながらフランス語となっている。
すべてのカリキュラムを行うには、300時間ほど必要で、その内容は膨大なものである。一つの単元が終わるごとにテストのための画面も用意されている。
この教育ソフトがいかに細かい内容になっているか一つの例を紹介することにする。第4巻の販売編であるが、顧客がHAシステムの販売店に自宅のHAシステム導入の相談にやってきたとする。あいにく担当者は他の顧客と電話中ですぐに応対することができない。
そこでどうするか二つの例が動画で紹介される。まず第1の例は、顧客を相談ルームに案内してそこで待たせ、数分後に「どうもお待たせしました」とHA相談員がやってくる。第2の例は顧客を相談ルームには案内せず他の場所、ショールームのようなところで待たせる。電話を終わった相談員が相談ルームにいって待っており、そこに顧客を案内する。
当然であるが前者が悪い例で後者が良い例である。前者は二つの間違いを犯している。まず相談室で待つ場合、顧客は緊張しがちである。さらに座って待つ顧客のところへ相談員が立って入ってくると、どうしても相談員の方が人間関係として上位になってしまう。
さらにショールームで説明するときは顧客の方に商品の正面を向けるべきであるとか、事細かな内容になっている。フランスでもHAのマーケットはまだ小さい。人口が多いだけに日本の方がむしろ大きい。それなのにこんな教育ソフトを制作する意気込みには感心してしまう。
ここで使っているのはシンフォリック(Synforic)のHAシステムで各戸に付けられたマイクロPBXと管理人室に置かれたセントラル・ユニットをペア線で結んでいる。管理人室にはミニテルの端末が置かれ各戸のモニターができるようになっている。
各戸の制御モニターユニットはサーボシステム(Servosystem)と呼ばれるもので、セキュリティー、プログラマブルタイマー制御、温度表示、電話・ガス・電気などの使用量表示、インターホンなどの機能を持っている。
 |
ドモティックが導入されたマンション
 |
シンフォリックの住戸ユニット
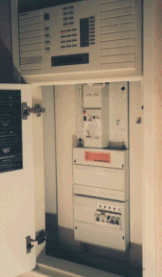 |
住戸ユニットの裏側は分電盤になっており合理的なレイアウトになっている。
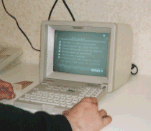 |
管理人室にあるミニテルの端末
フランスにはこのシンフォリックもその一つであるが、HAシステムを開発するための2つのコンソーシアムがある。シンフォリックには、Synforic Development、Matev、Tonnaなどがそのメンバーである。
もう一つはChineneグループで、こちらの方にはPhilips、Merlin Gerin、Landis et Gyr、I & Tなどが参加している。
シンフォリックが電話線を主体にしているのに対して、Chineneグループは住棟バスとして同軸ケーブルを使っているのが特徴である。
住戸内ではBati-Busが使われ、同軸ケーブルの住棟バスではI & Tが開発したMedia-Busが用いられている。住棟に設けられたセントラル・ユニットを経由して外部には電話回線で結ばれている。
SERENA−MAIF
ここではニール市の500人程の高齢者を対象に電話による24時間サービスを行っている。センター側で電話を受けると自動的にパソコン画面にその顧客のデータが表示される。
データを見ながら電話で応答し、適切な指示や処置をとる。センターには医者も待機しており、専門的な指示も可能である。
日本でも販売されている介護保険は、セレナ社の経験ではフランスではあまり受け入れないようである。むしろ高齢者の求めに応じて的確な情報の提供が最も重要であるという。彼らは遠隔監視もあまり有用ではないと考えている。
さらにDOMOBAT社と協力して、高齢者に合わせた住宅のリフォーム・ビジネスを計画中である。キッチン、バスなどを改修し通報通話ユニットを設置する。
これが最も効果的で、そのための支援をセレナ社は行っていく。住宅を改修して事故の前に事故がないようにといったリスク回避サービスが、これからの保険会社の使命であるという。
 |
セレナ社のエントランスホール
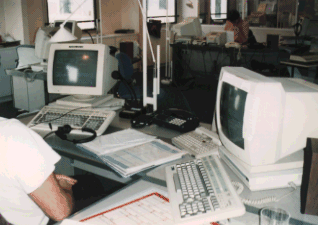 |
電話によるアシスタンス・センター
1992年に設立されたSILD社は、現在社員8人の若い会社である。ここのハード的な特徴は何といってもエシェロン・チップを使っていることである。
このチップとソフトウエアを組み合わせた、制御ネットワーク構築のためのツールであるロンワークス(Lon Works)は、すでに世界に500社以上のユーザーを抱えている。
イギリスのインテリジェントビルディングの研究グループの各種バスシステムの評価レポートでもロンワークスの評価が一番高い。エシェロンのデモ・ビデオにはこんなメッセージがある。
「現在さまざまな分野、さまざまな国で制御プロトコルの標準化を進めており、その標準を特定な分野に当てはめようとしている。しかし多くのユーザーとの研究の中で制御ネットワークの設計で直面している問題はあらゆる分野で共通であるということがわかった。あらゆる分野で実際にロンワークスが効率的に使われている現実を考えると、ロンワークスが制御プロトコルの標準になる日も近い。すなわち市場によって標準は決定するということである。」
SILD社のバスラインは4対のペア線で、その構成は、(1)テレメータリング用、(2)人工合成音声用、(3)(4)が予備となっている。
住戸モジュールは、3個のボタンと3つのLEDといった実にシンプルなものである。
ボタンは非常通報(赤)、ドアロック解除(グレー)、通話応答(グレー)、ランプは、呼び出し(黄)、作動中(緑)、非常(赤)となっている。
この住戸モジュールに液晶ディスプレイを付けることを検討中であるが、とかく考えがちなTVモニターや電話との一体化は考えていないという。新しいユーザーインターフェースに関してはロンドン大学のエルゴノミックス研究グループと共同研究を行っている。
地下室にはセントラル・モジュール(PCにミニテルボードが搭載されたもの)が置かれ、各住戸モジュール、さらにエレベータや共用設備機器、アクセスコントロールモジュールなどと結ばれる。
SILD社のHAシステムの機能は大きく4つに分けられる。 (1) セキュリティー(ガス漏れ、煙感知、アクセスコントロール、侵入検知) (2) 快適性(冷暖房制御) (3) エネルギー消費管理(電力量計測、課金) (4) コミュニケーション(リモートアラーム、インタホン、ボイスメール)
SILD社ではHAシステムをビルディング・マネージャーとして位置づけている。集合住宅をより住みやすく、故障のないように維持するためのシステムで、いわば賢いマンションの管理人というわけである。
 |
SILD社のHAシステムが組み込まれたドミトリー
 |
カードによるアクセスコントローラ
 |
フューチャースコープ
360°画面でのツールドフランス、3Dめがねをかけて見る3次元映像、画面とともにイスも揺れてスイスの登山電車に乗っている感覚が味わえるシネマダイナミック、観衆がシナリオを選択できるインタラクティブ・ムービーなどがある。
内容はつくば科学博などでも見られたものであるが、その規模、たとえばスクリーンの大きさはヨーロッパ最大というようなものばかりである。
また建物はSF映画に出てくるような、未来を感じさせるものばかりである。
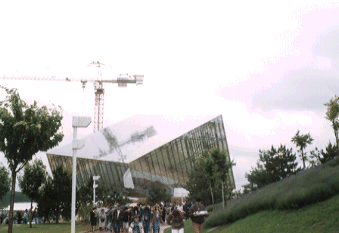 |
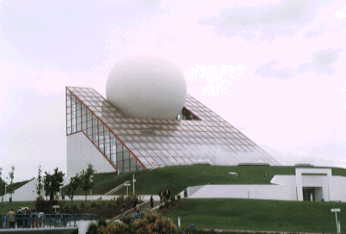 |
 |