
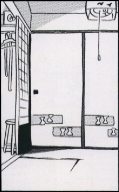

K+通信
第2号 1998年7月10日発行
発行 Kプラス
1年がたつのは早いもので、もう半分が過ぎてしまいました。また、暑い夏を迎えようとしています。皆様お元気でしようか。「ガム兄さん」で詩人平田俊子さんに出会って1年半、いろいろな皆様のお力を借りてようやく公演の運びになりました。
今回の顔ぶれは、詩人平田俊子と、いわゆる“アングラ”世代の、個々の場で大変魅力ある芝居を作ってきた役者達、それに文学座の若手気鋭の演出家との組み合わせです。
平田俊子さんの大変魅力ある新作「血まみれのんちゃん」で、“アングラ”世代の役者達が、その時代を飲み込み通り過ぎ、今をどう受け止めているのか、演出を軸として劇場で何かをきらめかせる瞬間を味わっていただけるのではと思います。
あまり片意地はらず、楽しくおもしろいものにしたい、個々の役者の新しい面をお見せしたい....、希望は膨らみますが、さあどうなるのか...。
暑い時期、小さな劇場ですので、電話で必ず予約を入れていただき、なるべく涼しいかっこうできていただけると良いと思います。そして終演後、そのままバーに開放したいと思っています。つまらなかった方も面白かった方もどうぞ一パイやっていってください。皆様のご来場を心よりお待ちしています。
Kプラス 佐藤和代

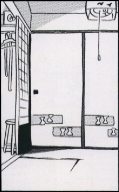

平田俊子
和代さんに会うと悪いことがおきる。
はじめて会ったのは96年の11月、高田馬場のプロトシアターだった。わたしの書いた『ガム兄さん』という芝居を和代さんがみにきてくれて、出演者のひとりの米田亮さんに紹介されたのだ。その日は少しおしゃべりしただけだったから、何事もなく無事に終わった。
年がかわって97年1月のある日、新宿の喫茶店で和代さんと待ち合わせて会った。来年芝居をプロデュースしたいと思っているのだが、その台本を書いてくれないかというお話だった。和代さんの話に耳を傾けながら、わたしは半分上の空だった。うちを出る直前にかかってきた電話のことを考えていたのだ。電話は夫からだった。3日前、「きょうはサウナに泊まる」といって家を出たきり、夫は帰ってこなかった。3日ぶりに声を聞く夫は、「お前とは離婚する」と突然いった。それだけいって電話を切った。本当なら芝居どころじゃないはずなのだが、書かせてもらいたいと思って依頼を引き受けた。
それから10日後、和代さんの家の新年会に招待された。地図を頼りに出掛けていくと、芝居関係の人が2 0人ほどいてにぎわっていた。夫は相変わらず帰ってこないし、わたしはこれからどうなるのだろう。不安な気持ちを紛らすようにその場にいた人たちと話し込むうち、終電の時間は過ぎていた。「泊まっていけば?」という和代さんの好意に甘えて、何人かの人と一緒に泊めていただいた。
次の朝10時ごろ家に戻ると、マンションの前に大きなトラックがいた。どこかのおうちがお引っ越しなのだな。そう思いながら階段をあがると、わたしの家のドアがあいていた。部屋のなかには夫と引越し屋さんがいて、家具を運び出す支度をしていた…。
不幸はこれだけでは終わらない。その後も和代さんに会うたびに、かばんが壊れたりお皿が割れたり階段でころんだりと不吉なことが必ず起きる。こんな人と組んで芝居をやっても大丈夫だろうか。不安におののきながら書いたのが今回の『血まみれのんちゃん』だ。
『血まみれのんちやん』が完成したのは今年の1月。もっと早く仕上げたかったのだが、身辺がごたついて遅くなってしまった。和代さんに台本を渡す約束の日は、朝から雪がふっていた。それも、厳冬の八甲田山みたいな猛烈な吹雪。こんなことになるとは思わないから、「渋谷のハチ公に抱きつくか、またがるかして待ち合わせましょう」という約束をしたのだった。
和代さんは約束の時間よりいつも早くくる。30分も前にくるときもあるらしい。吹雪の日にそとで和代さんを30分も待たせるわけにはいかない。早めに家を出たが、雪でバスのくるのが遅れた上にずっとのろのろ運転で、渋谷についたのは約束の時間ぎりぎりだった。和代さん、今いくから無事で待ってろよ。バスを降りて走ると、ハチ公の前に、傘に雪をつもらせた和代さんがぽつんと立っていた。「和代さーん」と手をふるとぱっと顔を輝かせ、子犬みたいに駈けてきた。
『血まみれのんちゃん』は、吹雪ではなく、風の強い日のおはなしである。風の強い日にそとを歩くと、新聞紙やバケツやコンビニの袋が風に吹き飛ばされているのをみる。あんなふうに全身風まかせにしてすっ飛んでいけたらどんなに楽しいことだろう。でも、人は重たいこころとからだを抱えているから、なかなかそういうわけにはいかない。せいぜい片腕もぎとられ、どこかに飛んでいくぐらいのことである。
愛の学校
佐藤和代
イギリス、サセックス大学で客員研究員をしている夫とブライトン(ロンドンから1時間弱の日本で言うと湘南といった感じ)に1ヶ月滞在しました。ロンドンには海外公演で何度か来ていても、気持ちに余裕が無く芝居をじっくり観た事はなかったので、何かおもしろい物を観て帰ろうと思っていたところ、偶然建物としても有名なGLYNDEBOURNEというオペラハウス(1000人位入る)でオペラを観る機会を得ました。
日本でオペラなど観たことのない私は、それほど乗り気ではなかったのですが、なかなかチケットが取れないのに好運にも取れたという事と、ちょうど今回の芝居にでる大崎さんがスペインから来ていたので、3人で行くことになりました。5時半開幕、1時間半上演し、1時間半休憩、その後1時間半の上演ものです。夫の友人のデービットが蝶ネクタイを貸してくれて、正装してシャンぺン、サーモン、パン、紙コップを持って行くよう教わりました。3時にアパートにタクシーが迎えに来て、私たちはせいいっぱい気取った恰好して乗り込み、30分程森の方に行った所にある広大なマナーハウス(領主の館)に建つ近代建築のオペラハウスに到着しました。
タクシーの中で私たちは事態が飲み込めず、「なぜこんなに早く行くのかな」「からかわれたんじゃない」「本当にお弁当持って行くのかな」等など、半信半疑でいたのですが、着いてびっくり理由がわかりました。どうやら休憩時間の食事のテーブルを確保するためだったのです。(勿論レストランは有るが、安い方は予約で一杯、高い方は有るらしい)ロビーは真っ黒な服に蝶ネクタイ、高級ホテルのボーイさんの集会かと思う様な有り様で、女性もきらびやかにドレスアップしています。(ただし皆中年以上)そしてピクニックバスケットを持っているのです。
あっと言う間にロビーは個々の家のリビングが引っ越しして来た様に変身してしまいました。テーブル、椅子、花、ローソク、テーブルクロス、お皿、数種類のグラス、沢山のご馳走、そして、始まる前にもうシャンペンを飲んでいるテーブルもあります。あいにく天気が悪く、雨が降っていなければマナーハウスの広大なイングリシュガーデンでするのだそうです。私たちはすでに遅い方で設置してあるテーブルはいっぱいだったのですが、エレベーターでちょつと親切にした老紳士の好意でテーブルの片隅を取ってもらえました。
始まる前に皆ロビーのバーで飲みながら待っています。(まるで満員電車のよう)会場の案内をする人たちも皆黒服に蝶ネクタイなので区別がつかなかったのですが、観察しているとどうも赤いリボンのついた金メダルを首にぶら下げている人がそうらしいのです。はじめは偉い人なのかと思いました。何故かというとそのメダルをお客に自慢下に見せて談笑しているのです。想像ですがボランティアの人たちなのでしょうか。
そして開幕、出し物はモーツアルトの(COSI FAN TUTTE)「愛の学校」で、古典的に上演するのではなく現代的にアレンジして(例えばシェークスピアをジーパンでやる様な感じ)あり、オペラらしいオペラを観たかった私には、装置無し、衣装は普段着、言葉は解らないで眠くてたまりません。(イタリア語を英訳にして字幕がでる)もちろん、他の人たちは楽しんでいます。(喜劇らしい)隣の老夫婦はご主人はいねむりをしていたのですが、失恋かなにかの悲しい歌の場面で奥さんが泣き出したときには、起きてやさしく手をさすっていました。(やさしいなあ)そして休憩、これは圧巻でした。
ロビー(3階まである)は大宴会場となり、そのウォチィングはとても楽しいものでした。日本のお花見のような感じでしょうか、地面にピクニックケットを敷いてやっている組もあります。テーブルと椅子を持参の人たちもいます。3人で紙コップにワインを注いでおにぎりで震えながら(すごく寒い)ホソボソやっていたら、その老紳士がグラスを貸してくれてシャンペンを振る舞ってくれ、コートとシャンペンそれにサーモンは絶対必要だ、今度来るときは是非持ってきなさいといいました。特に上流階級の人達ではなく普通の人達です。毎日日替わりで演目が変わるとのことです。
あーこの人達は芝居やオペラを観に来る自分を楽しんでいる、人生を楽しむ方法の一部にオペラがあるのだなあと思いました。こういう場はもちろん日本にはないし、この国でもここまでのものは珍しいのかもしれません。何故かというと寒い時期は開かないので6月から10月までだそうですが、もうすでに予約でいっぱい、キャンセル待ちなのです。これだけを目的で、ニューヨークから来て、観て、とんぼ返りするファンもいるとか。
いままで芝居は演じることでしか考えてこなかったけれど、観る側で芝居を考える事をしました。こんなのがあったら楽しいだろうなあ、また行きたくなりました。
「ガム兄さん」……頑張ってたで賞!
菅間 勇
ああ、これはいまではもう珍しい部類にはいったアングラ、いやクラック(Crack)芝居がやられている。この「ガム兄さん」の作者は、たぶんぼくと同年代だろう。そう、この作者の名をハッキリと憶えている。いまから十数年前に、現代詩の最前線で活躍しはじめた女流詩人の平田俊子さんだ。でも平田さんが芝居の台本を書いてるなんて知らなかった。
ちゃんとみていたつもりなんだけれどぼくにはこの芝居の顛末がほとんどよくわからなかった。でも、この芝居は妙におもしろかった。
筋書きがわかっているわずかな範囲で、というかほとんどぼくの勝手な思い込みでこの「ガム兄さん」の物語を思い出してみると……、失踪したじぶんの女房の行方を探っている中年男(米田)が、失業中の義理の兄(失踪したじぶんの女房の実兄=龍)のところへ足繁く通ってくる。訪問の目的は、どうやら義理の兄は失踪した中年男の女房からいまだに仕送り(?)を受けているらしく、その手蔓から中年男はじぶんの女房の行方を探りだそうということらしい。
だがこの芝居は、中年男(米田)のじぶんの女房の行方の探索線を重点に書かれているかというと、どうも書かれていないような気がする。中年男(米田)は失踪したじぶんの女房を、兄(龍)はじぶんの仕事を、真剣に探している風には少しもみえないし、作品の終盤に失踪した女房(妹)らしき人物は登場するにはするのだが、そこにもあまり重点が置かれていない。むしろこの芝居の面白さというか不可思議な点は、あるいは作者として、演出として観客に体験させたいと願っている世界はといいかえてもいいだろうが、それは、この作品の主人公の中年のふたりの男たち、人生の折り返し地点で迷子になってしまった中年男たちの内面に存在する空虚の露出の仕方とその空虚との奇妙な遊び方(させ方)の方にあるのではないだろうか、そう思えてきてしまう。
なぜなら、このふたり、とんでもなく仲がいいのだ。中年男(米田)はじぶんの女房の失踪にかこつけて、兄(龍)はじぶんの職探しにかこつけて、夜毎ふたりで会い、無駄話ばかりして楽しそうに時をやり過ごしている。なんだかよくわからないのだが、このふたりのあまりの楽しそうな無駄話と仲の良さが、この芝居を独自な雰囲気に仕立て上げているのは確かなことだし、事実の探索のことなどどこかに置き忘れてかまわないと思えるくらいの比重でそのふたりの楽しい会話が巧みに演出されているからだ。
今夜もその中年男は義理の兄のところへ遊びにきて楽しそうに無駄話をしている。そこへ、ふらりとガム売り(あのチューインガムだが、そんな職業あるはずないじゃんか)が、ガムを売りにくる。このガム売りの登場が、きわめてアングラチックで面白いのだ。そのガム売りは、この世にありそうもない味(これももう忘れてしまったが、たとえば焼き秋刀魚の味がするガムとかハムのサンドイッチの味とか、カッパエビセンの味がするガムだ)のガムをふたりに売り込む。兄は、義弟の中年男の制止にもかかわらず、ガムを買う。そしてテイストする。どうやらそのガムは、ガム売りのいう通りの味がするらしいのだ。兄は、そのガム売りがというよりガムが非常に気に入り、ますますいろいろなガムを買い、嬉しそうにテイストする。ガムのかたまりが、口のなかでゆで卵ぐらいの大きさになってしまっているのに、嬉しそうにガムを噛んで、うまいうまいと嬉しがっている。やがて芝居は、ここから終盤にむかっていく。けれどこの芝居は、観客としてのぼくたちが、終盤の意味をとらえそこねてもいい気がする。
作者の平田さんは怒るかもしれないが、この芝居は終盤にそれほどの意味はないといっていいと思う。なぜなら、終盤に意味を屹立させたいのなら、前半のふたりの男の楽しそうな芝居にどこか意味へ向かう伏線を張るはずだからだ。意味へ向かう伏線があれば、必ずふたりの楽しそうな会話はその箇所で渋滞を示すことになる。けれども、ふたりの会話に渋滞は微塵もなかった。
この芝居は、ふたりの中年男たちの奇妙なほどの仲の良さと100%フィクションの存在としてのガム売りの舞台上での存在の仕方に、面白さが加味できて不自然さを露呈していなければ、さらに口のなかでゆで卵ぐらいの大きさになってしまっているガムのかたまりを嬉しそうに噛んでいる兄の光景を楽しい親近感のなかに露出できていれば、すでに貴重で奇異な感受性を十分に舞台で達成していて、それがこの芝居の「意味」であり「価値」であると思える。
たぶんこの不可思議な芝居の本質的な感受性は、幼年期の幼児たちのママゴト遊びなのだ。そして、この芝居の意味は「現在」という「空虚」に「怠惰」あるいは「懶惰」という姿勢で対峙しようと試みていることだ。
失職という憂き目にあった男の空虚感。女房に逃げられた男の惨めさと空虚感。そうではない。そんなことを作者や演出がいおうとしているのではない。この台本作家は、失職という憂き目にあった男の空虚感や女房に逃げられた男の惨めさと空虚感といったものを取り上げるアクチュアルな社会派作家ではありえないからだ。
職を失ったから「彼」は空虚になったのではない。女房に逃げられたから「彼」は空虚なのでもない。「彼」やぼくたちがもともともっている生への空虚、それぞれの内面のなかで水面下に沈んでいた生きることへの空虚感が失職や女房に逃げられた事件で露出してきた。失職や女房の失踪は、それぞれの内面に沈殿していた空虚を露出する引き金に過ぎない。ここが、この台本の無意識の優れた表現への分水嶺であり、ぼくたちを惹きつけるなにかであり、「現在」をなんとなくねらい撃ちしている姿勢の予感を感じるなにかなのだ。
男たちは、「空虚」という大海のなかで、手漕ぎの「懶惰号」という名の小舟に乗って、どこかの岸辺にたどり着こうとしている。しかし岸辺は、どこにあるのか誰にもわからない。北か、南か、東か、西か、まったくわからない。けれども、たどり着こうとしている。ここでいま大切なことは、その岸辺の位置を安易に想定し、方向舵をその方位に確定することではない。とにかくどこかへたどり着こうと試みる、そのことがいま大切なことなのだ。それが、無駄な努力でもだ。平田俊子さんは、そういっているように思えた。
最後に、平田さんは優れた現代詩人であることはわかっていたが、ぼくたちの「生活」のなかから「懶惰」ということの意味・無意味を素手で取り出すことのできるたぐいまれな台本作家であることを、この「ガム兄さん」でぼくは知らされた。
ぼくには、この「ガム兄さん」という奇妙な芝居が、そう見えました。
あなたには、どう見えましたか?
url:<http://www4.justnet.ne.jp/~sugamapotetodou/>
(注)菅間勇さんのホームページから転載させて頂きました。
Kプラス